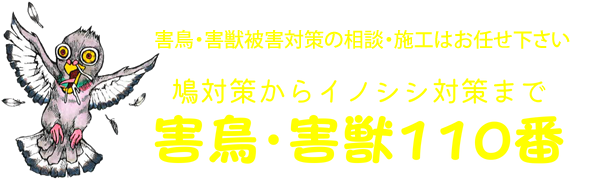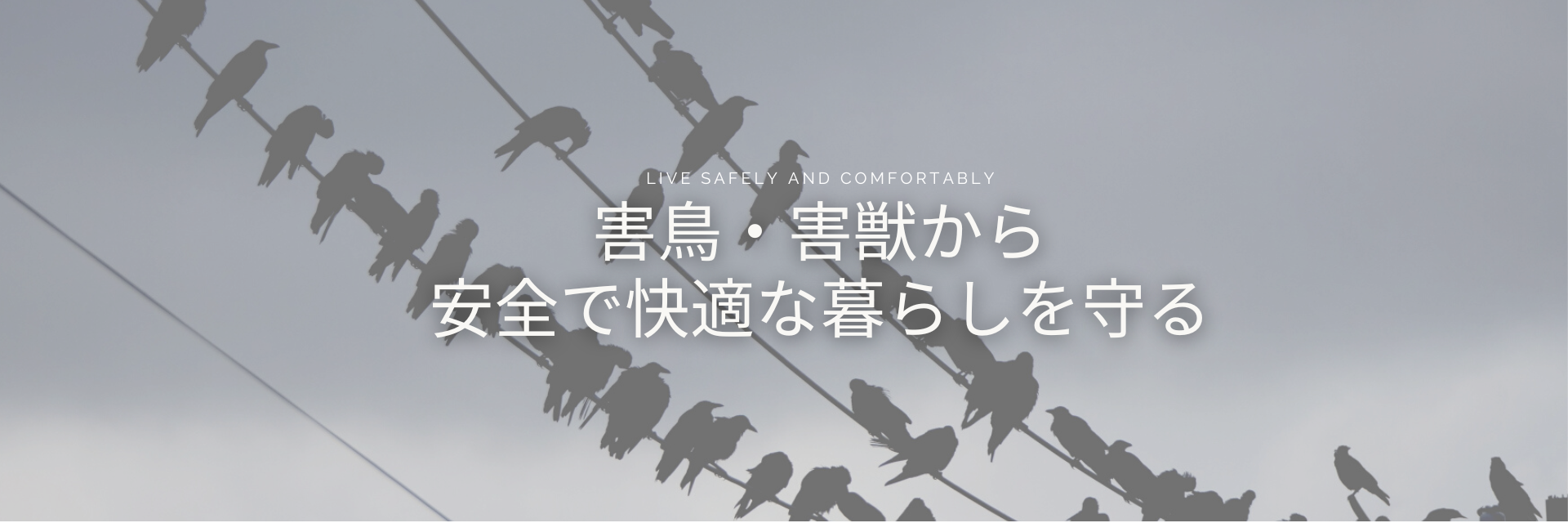ハトやカラスなどの害鳥・イノシシやシカなどの害獣対策のエキスパートとして
【害鳥・害獣商品の販売】と【害鳥・害獣対策工事】の2つの部門を展開、
付加価値とサービスの提供に真摯に取り組んでおります。
ハトやカラスなどの害鳥・イノシシやシカなどの害獣対策のエキスパートとして
【害鳥・害獣商品の販売】と【害鳥・害獣対策工事】の2つの部門を展開、付加価値とサービスの提供に真摯に取り組んでおります。
防鳥資材販売
当社では230種以上の防鳥資材を販売しております。
商品別の施工法など細かな技術サポートはもちろん、鳥の行動生態をふまえた初期段階のご相談なども承ります。
20年以上の経験とトータルなノウハウを持つ当社だからこそ実現した業界唯一のサービスです。

害獣忌避剤販売
イノシシ・クマ・シカ・ヘビ・マムシ等の獣害対策には、各種忌避剤(きひざい)を取り扱っております。
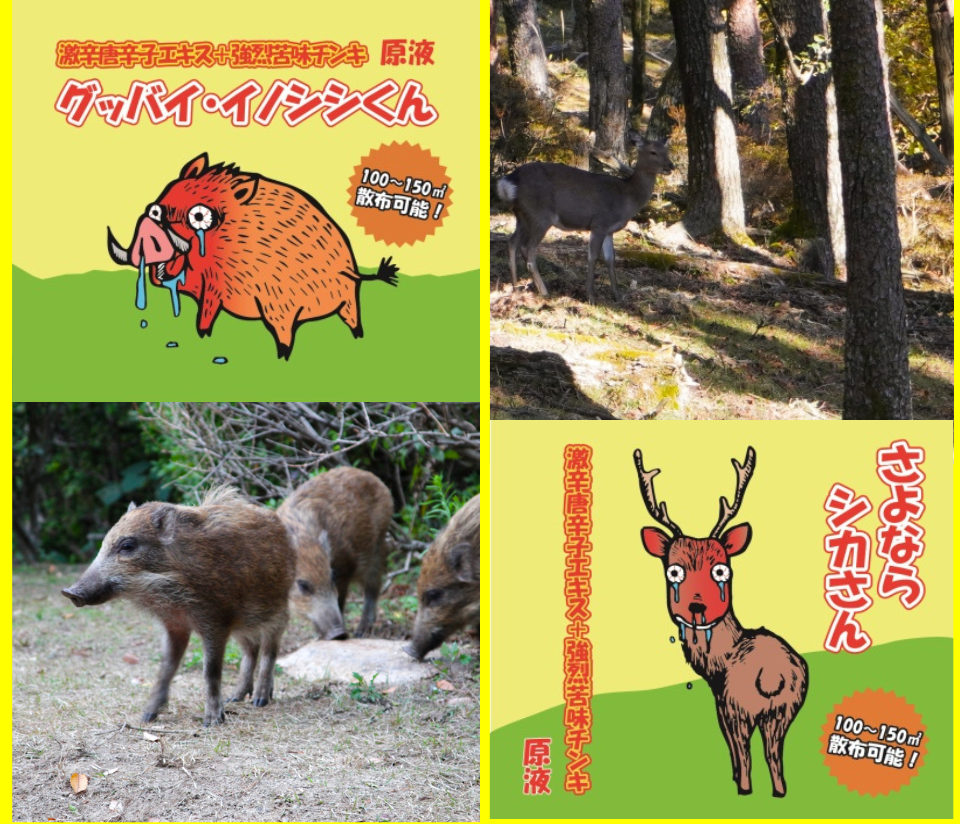
鳩・カラス・ムクドリなどの
防鳥資材販売
当社では230種以上の防鳥資材を販売しております。
商品別の施工法など細かな技術サポートはもちろん、鳥の行動生態をふまえた初期段階のご相談なども承ります。
20年以上の経験とトータルなノウハウを持つ当社だからこそ実現した業界唯一のサービスです。

イノシシ・シカ・クマなどの
害獣忌避剤販売
イノシシ・クマ・シカ・ヘビ・マムシ等の獣害対策には、各種忌避剤(きひざい)を取り扱っております。
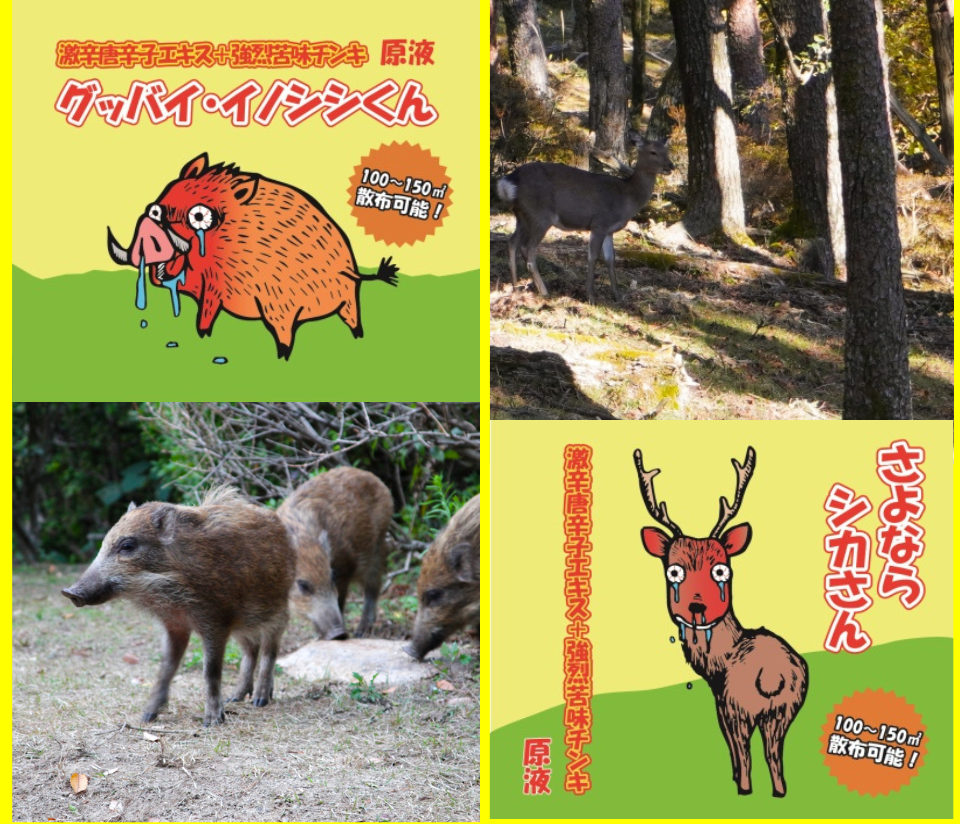
レンタル品
鳥獣害防止協議会推薦!全鳥獣害に対応
音声による撃退機 鳥・獣撃退スピーカー
仲間の悲鳴が効果てきめん!!
上部には太陽光パネルが装備されており、蓄電池で作動する為、電源コードは不要。
重量も軽く、簡単に持ち運んで設置する事が出来ます。
・近隣からの苦情等がないよう、音量に注意し音源から離れないでください
・効果的な範囲は1000㎡以内です
・建物の周辺・田・畑などで使用してください

ドローンによる鳥獣・害獣対策
鷹匠ドローン
仲間の悲鳴が効果てきめん!!
上部には太陽光パネルが装備されており、蓄電池で作動する為、電源コードは不要。
重量も軽く、簡単に持ち運んで設置する事が出来ます。
・近隣からの苦情等がないよう、音量に注意し音源から離れないでください
・効果的な範囲は1000㎡以内です
・建物の周辺・田・畑などで使用してください
※現在取扱停止中

ご相談など、お気軽にお問い合わせ下さい。